
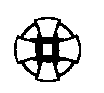
21世紀が近くなり今世紀の教育を振り返るとき、今からおよそ1世紀前に書かれたラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の最後の力作「日本--その解明への試論」(Japan--an Attempt at Interpretation)の中に当時の日本の教育をグローバルな視点から非常に純粋な心で批判した1章が思い出される。彼は1890年に日本に住み着き、心から日本に惚れ込んで帰化した。そして1904年にここで骨を埋めるまで、日本の国のすばらしさをその流麗な重みのある英文で世界に知らしめたため、ハーンの描いたイメージにひかれて日本に住み着いた有能な外国人は多い。そして晩年には全精力をこの本にそそぎ込みすぎて、これがアメリカとイギリスで同時に出版されたときには命が燃え尽きていたほどである。その中で彼がふれている3つの点に関して現代の教育事情との関連から思いつくまま書いてみたい。
幼少時のしつけと学校の集団生活
鎖国が終わり、西洋文化に追いつけ追い越せと全国民が「教育」されていたはずなのに、彼の目には、西洋とはまるで反対のやり方で教育が行われていると写る。1世紀も前から「日本の教育の目的は、人に頼らない独立した精神の持ち主を育てることでは決してなかった。逆に、身動きもできないほどぎっちりと作られた社会機構の中でそれなりの場所を占めて、周りに合わせて行動できるような人間を作ることであった」という。
西洋の家庭教育では、幼少時に体罰を加えたり、食事や遊びを取り上げるなど、出来るだけ厳しいしつけをする。年齢がすすむにつれて緩めていき、独立心に富んだ自立の人間を創ることを目的とした文化だ。その中に育った彼は、西洋と反対に小さいときに我がままのし放題を許す日本社会の教育を興味深く観察する。そこでは学校という集団生活の場が初めて自我を抑えることを子供達に教え、動きのとれない組織の中でも通用する人間にして追い出す。
「道ばたの穴でさえも五つ、六つの子を憎む」とよく言われたものであった。それほど手のつけようがなかった子供をしつけるのは学校の集団生活であった。ところが、学校でしつけをするのは教師ではなかった。昔の教師は厳しかったとよく言われるが、100年も前から、学校の教師は師というよりむりしろ友人のようだったという。クラスという集団生活の中で個人を規制していく力はクラス全体から生まれる無言の力、大きな考え方だった。その空気の中から自然発生的に、その中心となるべき人物が選び出され、その人物はクラスの空気をよく知っていて、教師以上の影響力を仲間に与えた。だから利口な担任教師は、言いにくいことをクラスに言わねばならぬ時に、そういうボスをうまく使ったという。学生も、人生のこのような早い時期に自分の意見を言うことを抑えて、全体の意志に従うことを生活の知恵として覚えていった。日本人の集団にはよくあることだが、そこでも一人の人間が全体を支配するという構図は存在せず、常に個人を支配するのは全体の空気だったようだ。もしこの空気に逆らったらどうなったか。そこで待ち受けるのは村八分であった。学校内はもちろん学校外の生活でも 完全に仲間から無視されて、皆の前できちんと謝罪の態度を示し皆がそれを認めるまでは、口さえきいてもらえなかったという。
これは現代風に言えば「いじめ」ということになるのだろうが、それは日本のような小さな島国であふれ出さんばかりの数の人間が、大きな喧嘩もせずに生きていくための知恵だったのかもしれない。今、個性化とか特色化とか急にかけ声をかけ始めても、100年前からの「伝統」が急に変わるはずもないが、仮にそうなったとしたら、ただでも熱しやすい国民性が刺激されて皆が自己主張を始め、個性と個性がぶっつかりあって国中が大混乱に陥り、収拾がつかなくなる可能性は大いにある。それを見抜けないほど国民は馬鹿ではない。現に「個性化」といっても小さなワクの中に入れられた個性化であり、枠を越えたとたんに圧力を加えられるか、無視されるかだろうから、外から見ると、「これが個性化?」ということになるのだろう。
ただこの何十年かのうちに生徒の集団が持つ、この伝統的な「教育力」に異変が見られるようになったような気がする。自然発生的に出てきていたボスがいない。5〜6人を越える集団ができない。ましてクラスや学校で1つのことをやろうとしてもバラバラで、ほとんど達成感、連帯感ももてずにすべてが終わる。
知らず知らずのうちに最大の影響力を与えて、基本的な生活習慣や発想の仕方の源を生徒の内面に創り出していくのはなんと言っても親だと思われるが、両親とも仕事に出ている家庭では心を通じ合わせるだけの時間もとりにくいし、ましてじっくりとしつけのできる状態ではないことが多いようだ。しかし仮に一方の親が定職を持たないにしても、核家族化した家庭で親は子供と過ごす時間をどう使っていいか学んでいないので、塾・教室通いに追いやって、この世に生を受けたときの純粋な心は知らぬ間に風化されていく。
大人の労働時間が短くなるのに伴って、子供同士がグループを作って遊ぶはずの場も子供スポーツクラブなどに組織されて暇つぶしの大人が仕切る場になり、子供が自分達だけで子供なりに試行錯誤しながら人間関係を作っていく場は日本の社会から姿を消していく。しかもそういう場を取り仕切る大人は、子供の独立心を育てる気持よりも、自分の職場の中でイニシャティブをとれないことの代償行為として、自分の趣味・優越感を広げる場に利用している場合が多い。大人に仕切られた場面でしか行動する機会のない子供は結局自発的には動けない人間となる。自然発生的な子供のけんかも大人が制止して、けんかの仕方を知らないで大きくなった子供は、いきなり相手を殺してしまっても自分で何をしたかの意識もない。自然な子供同士の人間関係を確立できない子供達が放り込まれた学校という不安定な社会で、登校拒否が起こるのは当たり前で、ちょっとカウンセラーの配置を増やすくらいの対症療法で解決の方向に向かうと考えるのは現状認識が甘すぎる。
よくあることだが、この夏休みにも小さなことがあった。成績が思わしくないので課題を与えておいて呼び出されたY君、約束の10時になってもいっこうに姿を現さない。夏休み前に大きな字で時間と場所を書いた紙を渡してあるし口頭でも確認してあるので、忘れているわけはないと思いつつも、電話をしてみる。応答はない。気にかけながら、とりあえず他の用事をすまし、2時間後にまた電話する。今度は本人が電話口にでる。
「どうしたんだ?」
「寝坊しました。」
「どうして起きたときにすぐ電話でこっちに知らせないんだ?」
「寝坊なのに、知らせなきゃいけないんですか?」
ここで、こっちの堪忍袋の尾が切れる。
「お前、何考えてんだ。人がわざわざ休みを犠牲にして待っているのに、2時間も待たせおって。お前、人の時間を何だと思ってんだ。課題を持って、今すぐすっ飛んで出てこい。」
ということになって、Y君青白い顔をして15分後に姿を現す。確かにY君にとっては嫌いな英語の課題を課された上に、彼にとっても休みを返上して「指導」を受けさせられるのはいい気持ちがしないのは分かるが、彼には自分が寝坊したあとも私という人間が待っていて気にしていること、自分がある時間に来ると言った約束を破る結果自分が人に与える迷惑や自分の信用の失墜により今後相手との関係で不愉快な場面に遭遇するはめになる可能性については思いも浮かばないし、教えられたこともない。だから
「お前、今までこんなことしょっちゅうやっていて何もなかったのか?」
「いえ、クラブでも先輩に同じこと言われました。でもオレよく分んなかったんだけど、そういうことなんですね、先生。オレこれからそうするよ。やっとわかった。」
という具合に、この年になって彼はこの世に「他の人間もいること」を学ぶことになる。
そのような不安定な人間関係で成り立つクラスだから、お互い級友同士の警戒感は予想以上に強い。友人にも心の内面は出来るだけ見せない生活の中で、精神的にはできるだけ接触しないでやっと保たれている平衡状態だ。だからその中で目立つことをすることはその平衡状態を壊す行為でもある。そのような場合にはクラスの自衛本能が働いて「いじめ」で現状復帰がはかられる。もちろんその目立つ存在が非常に強力で個性的であればヒーローが誕生する形になり、そこで新しい平衡状態ができる場合もないわけではない。しかし高校では生徒の輪切り状態が極度に進行している状況なのでこんなことは奇跡に近いことだ。
日本の社会集団では自浄作用がないことが多いが、教室の生徒の集団でもそれは言える。最近では大学祭をはじめ、学校祭で真面目な取り組みを期待することはほとんど出来なくなった。学校祭で何をするかなどの提案をクラスで話し合う場合、真面目な意見は浮いてしまう。半分ふざけた無責任な思いつきが「かっこいい」意見として全体を支配する。学校という不自由な組織の中に閉じこめられた生活の中で殻をやぶりたいという心理に迎合する考えが共感を呼ぶ部分があるが、全体が前向きの積極的な方向に向かないのでいらいらすることがある。前向きの力を後ろから引っ張る集団の力のモーメントの源は何なのか。これも探り出すときりがないのかもしれない。
金儲けと教育
「公立学校の教師の大部分は学生に金銭的な援助をすることができるほどの給料をもらっているわけではないが、やっと生活できる程度以上の稼ぎのあるすべての教師が学生に何らかの援助をしている。更に高等教育に携わる教師や教授達の間ではそんなことは当然のことのように考えられている。あまりにも普通に行われているので、特に給料の少ないことを考えると、こういう習慣があるために無理をせざるを得なくなっているようにも見える。でも極端な実例から分かることだが、教育の封建的な理想に対する妙な執着心、自己犠牲の満足感はこんな風には説明のつかないことだ」とハーンは述べて、ほとんど給料の全部を何年も多数の学生の衣食住から書籍、授業料までも与え続け、自分は芋をかじってほそぼそと生きていた教授の実例を引いている。更に外人教師が同じことをしてパンと水だけで飢えをしのいで生きるなんてことが考えられるだろうか、と感動している。そして彼は日本人教師より高い給料をもらっていながら傍観していて、学生には単なるティーチングマシン扱いにされることに対する不満を訴える。ハーンは更に続ける??「 師弟の関係はその力において親子の絆に劣るだけであった。教師は生徒のためにはすべてを犠牲にして顧みなかった。生徒は自分の教師のためならいつでも喜んで死んだ。それ故、襲撃に先立って、昔の恩師だけは、包囲された場所から逃がしたいと心を砕いた武将もあった」という。これは何も教育界だけの問題ではなく、程度の差こそあれ日本社会の人間同士の結びつきのあちこちに見られた現象であった。
このように人間の深い部分でしっかりと結びついた人間関係は、封建的と言われるかもしれないが、今の希薄な人間関係の中にいると一面すばらしい世界だとも思う。まさに犠牲と報恩の関係で人間同士が結びつき、浄化された精神の土台の上に信頼の絆がかけられ、相手から深遠な真理を丸ごと学ぶ。しかしハーンも言っているように、「このように人知れず行われている犠牲は人前に出すと、そのような人たちに苦痛を与えるだけで、このように書くことさえ、軽率の謗りを免れない」ことなのだ。そして何より大切なことは、これがすべて自発的なもので、強制されたものではなかったということだ。それなのに何と戦後の政府は教職を無理矢理に「聖職」に仕立て上げて教師に強要し世間に宣伝して、教師の給料を低く抑え込む手段に悪用し、教職の置かれた社会的不公平を正当化しようとした。教師は怒った、そして開き直った。その後この「聖職」という言葉はタブーになった。教師も教職員組合を組織して、労働者であることを誇りにし、ストライキを打ち、給料のレベルはかなりアップした。教職の社会的不公平はかなり改善された。これは必然であり、すばらしいことでもあった。
しかしこの過程で師弟関係の振り子は逆の方向に振れすぎた。教師は知識を与え、拘束時間に労働して自分のための金を受け取るという図式ができた。つまり生徒は金儲けのためのお客様なのだ。「学問に王道なし」とはよく言ったもので、何でもわがままが許される立場の王様である「お客様」がわざわざ大きな苦労を伴う学問に精進するわけがない。「余は学問を学んでやるからありがたく思え」とでも言い出しかねない「生徒様」のご機嫌をとるのが教師の役目になる。そしてご機嫌をとるのに抵抗を感じる教師の逃げ場は自分のために勉強する楽しみと報酬だけになる。一方生徒は、自分とはあまり関わりのない教師という労働者がその報酬のために労働をしている場面に学力のレベルによって振り分けられて、卒業証書をもらわないと社会で一人前に扱ってくれないからと考えて、やむなく通う。親の望みは一流大学卒というレッテルで、そのために、いやそれを口実にして、家庭でのしつけも犠牲にされるので、同情心や正義感のないご都合主義者の生徒がどんどんと増えていき、学校は教育以前の問題に振り回される。これは教育ではなく労働である。もちろん実業界ではなく教職を選んだ教師と いう人間は金銭だけにこだわる人種ではない。子供が嫌いではないのが普通だし、お人好しで純粋な心の持ち主がほとんどだ。しかしこの大きな流れを変えるには微力すぎる。
つまりこの1世紀の間に、日本の教育は、他人に対して「与えあう関係」から、自分のために「取り合う関係」に180度の転換をしたことになる。言い換えるとその中心は「献身」から「エゴイズム助長」への転換ではなかったのか。要するに学校教育は、人間社会において、エゴイズムを越えた人間本来の資質を高めあう場ではなく、個人レベルでの後生の経済的な安定のための投資であると認識されてきた。従って興味を掘り起こすことより、入試を乗り越える手段としての「勉強」に中心が移っていくのは当然の成り行きであった。しかも金が万能で、すべてを金で解決する日本社会では大学での勉強も金儲けのための準備教育となり、政府も産業と一体化してこれを後押しする。残念ながら、現代の学校教育のほとんどは日本社会で生き残るための「必要悪」になった。教育行政も給料の「12短」など昇級に1年分も差をつけて、教育内容を金ではかろうとする愚行を強行する。金銭で大きな差をつけて教師の士気を高揚させるとする方式が功を奏するとすればそれは教育の世界ではないし、そういう発想が自然に出来たり、不思議にも思わない輩が教育行政のトップに居ること自体が絶望的な状況であ ることを示唆する。
もうだいぶ前のことだが、都立高校にも補習科と称する「課程」を置いていた学校があった。いわば非公式な高校4年生の課程で、今の予備校の何分の1かの「授業料」を取り、大学入試への指導をして、大学に入れていた。生徒をよく知っている教師が高校から引き続いて教えるので効率もよく、家庭の経済的負担もごくわずかで、親や学生には大いに喜ばれ、教師も信頼感に支えられて充実感を持って教えることが出来たようだ。当時の行政は細かい規則にこだわって本質を見失うほど愚かではなかった。都立に優秀な生徒が集まっていたせいもあって、教師の方も自分の責任である3年間の課程を終えても、その可能性を信じて献身的にその後の生徒の面倒をみたし、生徒や親の方も学校を信頼して、そこには強い絆があったように思う。
その後教師が給料以外に金をとるとはけしからんということになり、一切の「副業」が禁じられた。その結果、親は莫大な金を払って、生徒は遠くの予備校へ時間と交通費を使って通う形が固定していった。もちろん多数の生徒を前にしてマイクで行われる授業の予備校教師が生徒を一人一人知ることが出来るわけもないが、生徒や親の気持ちの中に、高い金を取られたことで、何か「取ってこなければ」という損得勘定と、金がすべての日本では、高い金を払って手にするものは価値があり尊敬に値するはずだという固定観念が無意識のうちに作り上げられる。例外は別にして一般的には、予備校の教師だって金をもらう代償行為で教えるわけで、やはりそこには「取るために与える」関係しかなく、学生が落ち込んだときに頼れるような昔の補習科の親身の絆は望むべくもない。こんな関係などは煩わしいだけだと思われるむきもあろうが、このような親身の関係からその後の何十年にもわたる師弟の絆が出来ていくように思う。
行政からみた教育と実際の教育:
「おずおずと帽子を脱いで質問にきていた魯鈍な学生が、卒業したとたんに、堂々として図太い神経の悠然と構えた官吏に『変身』するさまほど度肝を抜かれることはない」とハーンは書いている。「変身」に当たるところに彼が用いたmetamorphosisという語は虫が蝶に脱皮するような「変身」を指すので、彼が驚いた度合いが想像できる。そして「学生が官吏に任用されるときの基準は学識の深さより、組織の中での管理能力、言い換えると、人の気持ちや動機を素早く読みとる能力なのである。いかなる状況が生じても顔色一つ変えず、簡単なことをちょっと尋ねてことの真相を即座に読みとり、親しい関係の人にも常に警戒を怠らず、決して本心をみせないようなわけの分からない人間でいること??その知恵を身につけることが実質的な卒業の資格となる。これは彼が長い学校生活の間に身につけたことであり、日本人としてまさに完成された人物ということになる」という。「このような精神と西欧の精神との間には計 り知れないほどの溝があるが、日本人の場合、ここで自分を捨てなければならない」ことが特徴的だという。「自分という1人の人間である前に、家族の一員、政府の役人であることが優先される。つまり社会の慣習にしばられ、上司の命令に従って行動することが求められる。いかに自分の考えの方が高潔で道理にかなったものであっても、夢にでも命令に相反することをする衝動に屈してはならない。ちょっとでも不用意なことを口走ったら、人生を棒に振ることになる。ただ黙って耐え、忠実に命令を遵守していれば急速に株が上がり、最高の地位にやがてたどり着くことにもなる。しかし皮肉にも地位が上がれば上がるほど、ますます締め付けは厳しくなる」とハーンは見る。
彼は続ける、「日本の官吏生活の最も救いようのない面は道徳的判断を自分で出来ないこと、つまり、自分の良心、正義感に基づいて行動する権利を持てないことである。地位の下の者が自分の地位を確保しておきたいと思ったら、上司の『お許し』を得なければ、人間としての信念や同情心すら持てないとはどういうことなのか。人間が完全無欠に作られていれば、この制度もうまく行くだろうが、人間性が今のようである限りこの制度には問題が多い。すべては大きな権力を一時的に委託された個人の人格に依ることになるので、非常に有能な部下でも、悪質な上司の元で働くことになったら、悪いことをするか辞めるかしかなくなる。強い人間だったら勇敢に問題に対処して辞めるだろうが、そういう人は50人に1人くらいなものだ。」
ここで使われている官吏という言葉を教育行政にたずさわる人々と置き換えてみると、教育は事務的処理ではどうにもならない部分をかかえているだけに、なお一層深刻なものになる。最近では校長教頭も行政の枠に押し込められて良心を売り飛ばした冷血の行政官という感じがすることが多いが、子供・生徒を育てる使命を負っている教師が、良心に反することをするよう強制されても、良心を偽って教えることはできない。良心を偽ったとたんに生徒と心は通じなくなり、教育は成り立たなくなるからだ。「良心の自由」は憲法でも保障されている当然の権利だが、それに反することを巧妙に今の上意下達の仕組みに組み入れられることがある。日の丸問題などもそうだが、手続き上は一応もっともらしく正当化できるように仕組んであるが、実に巧妙に既成事実を作っていき、それが一人歩きを始めるようになる。そして教育の現場に強制され、教師の良心を強引にねじ曲げようとする。なお悪いことに、それを意図的に仕組んだ最初の人間以外の中間行政職の人々にはその経緯の認識はなく、上意下達を実行することが正義になってしまうように組織上作られていることである。しかもそれを忠実に実行 することが摩擦もなく出世にもつながるとなれば、多くの人は無難な道を選ぶ。
かつては最高裁長官、文部大臣なども経験し、「教育基本法」を制定するのに執念を燃やした田中耕太郎は教育の本質について次のように述べている??
「教育は一般文化現象と同じく、私的、民間的性質を有しており、本来国家の活動の範囲外に位するものである。それは本来国家的起源のものではない。教育者と被教育者との関係(教育関係)は芸術家と作品との間のものと同様に、極めて個人的の関係であり、そこに国家の介入を許さないのである。このことは教育の最も本源的な関係である親子の間の関係及び学校教育が沿革上私塾的なものから発達した事実に想到すれば明瞭である。教育の国家的独占は、教育を国策の手段と見るナチ的、ファッシスト的又は共産主義的理念の所産に外ならない。」(田中耕太郎「新憲法と文化」)
日本にもこのように良心に基づいて公平な言動の出来る文部大臣がいたことは我々の誇りとすべきことだが、彼は更に「教育改革私見」と題する覚え書きで、国家と真理及び道義との関係について、次のようにも書いている。
「権力国家的思想即ち国家が正邪善悪に超越する存在なること又は国家が正邪善悪の尺度を規定し、国家に有用なるもの即ち正且つ善なりとの思想を排除すること。更に文部省の存在理由及び、機能を再検討し、これを存置するとせば、その活動を原則として教育の内容に関与せざる純粋なる事務的方面に限定すること」
ということを彼が敢えて述べたのは、文部省が過去に犯した重大な過ちに対する反省があったと思われる。文部省が中央集権的な官僚機構の中核として、人事行政面だけでなく、教育内容特に思想統制を強化し、軍部や右翼団体の勢力を傘にきて日本精神、教学刷新などを号令したことであろう。
しかし、トップが変わり時代が変わると初心は忘れられて、切り取った癌の根からまた新しい癌が出来るように、昔ながらの官僚体制の中で、間違った教科書検定や日の丸国歌の問題など巧妙な形で思想統制という癌が再発しかかっている兆候がある。
政治家は常にマスコミの目にさらされていて、悪者にされる。国会議員だと財産も表面上は公開される。実際ひどい話題も多いし、それだけ悪行も横行しているのであろうが、官僚や役人は実権を握っていて様々の形で権力を行使できるのに、ほとんど国民の目には見えてこないし、もちろん直接選挙で洗礼を受けるわけでもない。しかも短期間のうちに部署を変えられることも多いようで、請け負った仕事を終えたあと配置転換を受ければ、その仕事の責任はほとんど問われないようだ。
すべての行政機関に共通のことだが、制度や組織を変えるときに、実際に一番関わりを持つ人の考えを無視してことは秘密裏にすすめられ、明るみに出たときにはほとんど決定されていることが多い。企画する本人が企画されることに関わりを持つことになる人間より組織上、上位に配置されているとしても、当事者の考えを打診することすらしないのは傲慢そのもので、これで民主主義国家かと思う。仮に諮問委員会のようなものを作っても、実権を握っているのは官僚であることが多く、最初から予定された結論を用意していて、それに合わせて段取りを決めているのではないかと疑いたくなるような経過をたどる。
実際、この40年くらいの間に都の教育関係で、お役人主導型の大きな「改革」がなされて、長い目で見て良かったと思えるものは残念ながら皆無に近い。確かにどのような改革も良い結果と悪い結果が出て、それを比べることになるが、これは教育ということを真剣に考えざるを得ない学校現場にいて感じる正直な総合判断である。勤務評定が学校現場にどのような良い影響・悪い弊害を残したかを公平に調べたことがあっただろうか。そしてそれが教育関係者一般に公開されたことがあっただろうか。入学選抜方式も合同選抜から学校群制度へ、更にグループ制、単独選抜へと異常な変わり方をしたが、その度に都立高校の教育環境は歪められたと思う。学校群制度を作った当時教育長だった小尾乕雄氏は「受験戦争の弊害をなくすため」と説明した。しかし何年か経ってテレビのインタビューに答えて「あれは有名校倍増計画だった」と述懐した。しかしあの制度が始まった頃から、受験競争は一層加熱し、都立の商業工業高に入学する生徒が誇りを失っていったし、もちろん有名校倍増どころか、ほとんどの学校でレベルダウンを被った。この失策に対して小尾さんはもちろん誰も責任を追及された人はい ないし、その他の主任制、強制人事異動などの教育への影響の「公平な」分析や政策失敗の責任問題に関してほとんど何もなされていない。金がすべての日本では金銭の不正に関しては責任追及が厳しいが、それ以外では意外なほどの無責任体制がまかり通る。
教育は精神活動である。行政や管理職がそのことを理解できないとき、教育は破綻すると思う。精神活動に勤務時間のワクを無理にはめてみても実はあがらない。いったん教師になったら24時間、心は教師だと思う。目に見える成果は時間では計れない職業だから、教師に自由な精神状況を保てるように配慮することが賢い教育行政の手腕だと言っていい。目先のことだけを考えて、小さな帳尻を合わせることにのみ神経をつかっていると、知らぬ間に空洞化現象が起こる。
教育の本質に対する理解も持てない無責任な声に振り回されない教育愛と信念の教育行政を望むのは私1人ではないはずだ。
ハーンは心から日本を愛してくれた数少ない外国人だった。しかしすばらしいと思った日本人の心は幻想だったと気が付いたとき、絶望のどん底に突き落とされて死んでいった。何よりも心を大切にすると彼が信じていた日本人が、実は物質文明に毒されていたことを知ったからだった。もともと西洋の物質文明を逃れて日本にたどり着き、やっと見つけた別世界だと信じ込んでいた彼にこれ以上のショックはなかった。日本人の純粋な心が生き残っていた100年も前の日本ですら、彼に立ち直れないくらいのショックを与えた。今の日本に彼が生きて現れたら一体どうなることであろうか。