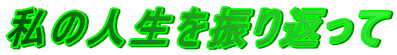
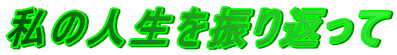
|
この世に生を受けて八十九年、というと我ながら呆れるほどに長い人生を歩んできたようだが、私自身にとっては、それほど長い感じはしないというのが本音である。恐らく人間、誰しもそうであろうが…。 しかし老いは確実に進みつつある今、私は、まだ記憶を失わないうちに 私は三,四才の頃、一年ばかり母の実家のある、やはり長崎県島原市の祖父母の居る家に乳母と共に預けられた思い出がある。多分一つ違いの姉が体が弱くて手が掛かり、私はなぜか丈夫に育っていたので、祖父母に手助けを頼んだのではなかったろうか。 長崎の家の思い出は、今でも不思議に思うのだが、日常茶飯事のことから、あたりの風景、家の間取り、すべてが頭に刻み込まれている。食卓にいつも並んでいた新鮮なアワビのお刺身、私の大好物だった。縁側には真っ白い子犬のポチが、手を掛けて私たちの食べているのを眺めていた。 私は母から送られてきたお人形を抱いて、ポチと一緒に外へ出た。祖父母や乳母や祖母の姪に当たるお姉さんや大人ばかりの中で、私はずいぶん甘やかされていたようだが、遠く家族と離れていた寂しさが子供心にもかなりのショックであったようだ。 やがて一年経って我が家に帰ってきたが、我が家は既に大阪を離れ、芦屋の家に移っていた。広々とした家! テニスコートもある! 桜の木の下には“あずまや”がある。橋のかかった大きな池! その横には小高い築山が… なんだか別世界に来たようで夢のような気持ちがした。 いよいよ家族が揃って、新しく幸せな日々が始まるのである。 父は二つ三つの会社の重役を務め、人の出入りも多くなり、広いと思った家も狭くなったのか、又母屋の続きに今度は現代風の大きな洋館を建て増した。 一番嬉しかったのは、ピアノのあるリビングで私たち娘3人がピアノを弾いたり、歌ったり、レコードを聞いたり自由に楽しめたことだった。そして隣は兄の部屋だったし、又その隣は私たち3人の勉強部屋になっていた。英語や数学の分からないところは兄がよく教えてくれた。 父の部屋は2階だったが、私の記憶では、よく巻紙を左の手に持って、持ったままくるくる回しながら、毛筆で手紙を書いていた姿が印象に残っている。 その隣は客間だったが、ステンドグラスのはまった綺麗な部屋で、中国から求めたのであったのか、中国風の彩色もあでやかな大きな屏風が異彩を放っていた。 広い家だったので家の掃除は女中(今で言うお手伝いさん)が二人、庭の方は男衆(おとこしゅ)が一人で受け持っていた。今思えば、よくも贅沢三昧な生活をしていたものだと思う。 恐らくこの芦屋時代が、父にとっても母にとっても生涯で一番豊かな、そして華やかな時代であったことと思う。 さて、私はこの家で、幼稚園、小学校、女学校、と過ごすことが出来た。私と二人の姉は、同じ神戸の兵庫県立第一高女に入学できたので三人一緒に神戸まで汽車通学をした。(それは、私が一年、次の姉が二年、上の姉が五年生の時でその一年間だけであったが)。 汽車通学といえば大阪の北野中学に通学していた兄が、毎朝忙しく家を出るのだが、汽車の時間に間に合わないと言って、白いゲートル(当時、中学生は大体ゲートルを使用していた)を片手に芦屋の駅に駆けだしていく姿が、今も目に浮かぶ。私たちが通っていた女学校の思い出というと、今の人たちには想像も付かないような厳しいものだった。忠君愛国精神で固められていた。先ず教育勅語という明治天皇の発令された詔に沿って教育は行われなければならぬ、ということで、その教育勅語を全部丸暗記せねばならぬのである。今でも私は覚えているがちょっとその一部を書いてみると、 「……吾が臣民よく忠によく孝に、億兆心を一にして世々その美をなせるは、之れ吾が国体の精華にして、教育の遠源又実にここに存す。汝臣民父母に孝に、兄弟(けいてい)に友に、夫婦相和し、朋友相信じ、恭倹己を持し、博愛衆に及ぼし、学を修め、業を習い、以て知能を啓発し……」まだまだ続くがこの調子である。 私たちは、ことある毎に直立不動してこの教育勅語を暗誦した。 私どもの同年輩の方ならきっとご存じのことと思う。この一事をもってしても、そのころの時代背景が想像できるのではないだろうか。 勉強もよくした。みんなまじめだった。時には反体制をとなえる人たちも、いたにはいたが問題を起こすようなことはなかった。 勿論一人で映画館に入ったり、友達同士で入ったりは許されなかったが、「保護者と一緒ならまあいいことにしましょう」と言う程度だった。ほんとに堅苦しい学校だったと今にして思うけれど、当時はそれほど感じなかったようである。 修学旅行で九州を一周したり、夏には淡路島の江井という海辺に行って十日間の水泳講習に参加したり、六甲の山を歩いて友達と語り合ったり、やはり若き日の思い出は尽きないものである。 さて、兄の話に移るが、兄は北野中学を卒業して次は神戸高商に入学する。このころから兄は密かにアメリカへの留学を考えていたと思う。卒業してまもなく、父母に自分の考えを述べたようだが、両親もさすがにすぐには決心が付かなかったようであった。二十二才の単身での渡米と、予定していた2年間という長い月日が父母にとって、どんな思いで聞いたのであろうか。しかし兄はことのほか英語が得意であったし、性格的に明るく、社交的で、音楽にも親しんでいたので しかしここへ来て思いもかけぬ事件が起こる。夏休みを利用して、自分で購入した自動車で、アメリカ大陸自動車旅行を企て、というのも後に、同乗した友人の話を聞いて分かったことだが、かつてのインディアナ大学時代の恩師や友人に会いたい思いと、又それを機会にアメリカ各地の主なる大学を見学し、尚、機会が在れば出来るだけ各集会に於いて講演し、日米親善の一助たらしめようと言う広大な抱負を考えていたのだと話してくれた。 旅行中のエピソードも色々聞いたがとても書き尽くせないので省くことにする。 この旅行の後、兄は、はからずも病を得、急性肺炎を併発して急逝するのである。勿論在米中の父の会社の方々や知人、友人達が必死の看護をしてくださったのだが、兄も病には勝てなかったようだ。帰朝を間近にしてのこの悲報が、我が家に届いたときの家族一同の驚きと悲しみ、之は筆舌に尽くせるものではない。 大きな抱負を抱えていた兄の心中を察するだに涙である。数ヶ月後兄の遺骨は父の会社の人に支えられて帰ってきた。運命の非情を経験した私たちだった。 ここから一足飛びに話を進めると、私が主人と巡り会ったのは、昭和十二年六月頃であったか?(といっても正式の見合いだった。) 私の母の従妹に当たる人が主人と同じ大阪の朝日新聞社の保健婦さんとして同期入社したという関係で、主人とは顔なじみであった由、その人の紹介で見合いをすることになったのである。 私は母と、主人は親代わりの義兄(遠藤みほ子の父親)と、そして母の従妹の保健婦さんの五人で会ったことを覚えている。たまたま、朝日ホールで催されていた演劇(喜劇だったと思う)を皆で見たりして楽しそうに大声で笑っていた主人が印象に残っている。 婚約の段階になった頃、北支(廬溝橋(ろこうきょう))事件というのが発生し、日本からも動員が始まったと言うことは聞いていたが、まさか私たちの上に降りかかってくるとは思いもしなかった。主人に赤紙の召集令状が来たのである。彼は在郷軍人陸軍少尉殿であった。軍服に着替えて挨拶に来た彼を複雑な気持ちで見送ったのだったが…。ここで又どんでん返しと言うことになる。幸か不幸か、軍医さんの身体検査の結果は、「胸膜炎の痕跡在り」ということで即日帰郷になったのであった。新聞社に勤務しているという事情もあり、無理に戦場に出なくてもお国のためのご奉公は同じだからという軍医さんの特別のお計らいであったようだと主人は後で言っていた。 それにしても「胸膜炎」と診断されたからには静養しなければならぬ。当時、多忙を極めていた新聞社での日常が、我が身を省みる暇を与えなかったのが原因であったのだろう。ともかく一ヶ月の休養期間を貰って主人は、山梨の温泉郷へ静養に赴くのである。従って、私どもの結婚の話は一時休止と言うことになった。
運命の分かれ道とはこんな所にあるのだろうか。ここで、この結婚が成立しなければ、現在の私は居ない。又、子供達も授かっていない。とよく考えることがある。不思議な思いがする。 両親にしても、一番大事な健康問題をおろそかには出来ない。せっかく進みかけた縁談だったがと、大いに考えたようであったが、又私自身も判断が付かない状態であった。一ヶ月後、再び私どもの前に現れた彼は、以前と変わらず元気な笑顔を見せていた。 再び話が戻り、私どもは結婚する。 昭和十二年十一月十六日であった。 新居は兵庫県西宮市樋之池(ひのいけ)、この名前の通り建物の東側に樋之池という大きな池があった。食用蛙が沢山いて夜ともなると、グワーグワーと蛙の大合唱が始まる。周囲は田畑にかこまれ誠に素朴な田園風景であった。(之は主人が見つけて気に入っていた)。 翌年秋、甲府から主人のお父さんが来られ、一ヶ月滞在された。二階の一間をお父さんの部屋にして、机や硯など主人が心配りしてあげたのが、ご満足だったのか、いつも漢詩など作って静かに過ごしておられた。休日には京都や奈良、高野山までも主人がご案内してあげた。このとき、沢山書きためられた漢詩を後に主人が屏風に表装して、大事に保存している。 ところでこの家も、私が妊娠したことで、大岡の実家に近いところに引っ越すことになる。当時はあちこち手軽に貸家があったので探すのに苦労はなかった。 さて、昭和十四年三月三十日、長男健夫が生まれる。この時、大岡の父は、既に胃ガンを病み、二階で病臥状態であった。健夫のお宮参りの時であったか、私が健夫を抱いて父に見せると、 「ほう、これはこれは快男児(甲斐の国をかけた)だな」とほめてくれて、こんな苦しいときにも洒落をいう父を偉いなと思った。お宮参りのお祝いにと持参したお赤飯を、ほんの一口食べてくれた。忘れられない思い出である。父は看護の甲斐もなく同年5月9日、他界した。父を失って、私はしみじみ親を失う寂しさを知った。決して子供を叱らない父だったが、父の姿が見えなくなった家の中は大きな穴が開いたようだった。私の一番上の姉が、淋しく一人残された母を気遣ってのちに同居することになる。 さて、次男乙彦は翌年十二月五日に生まれる。予定より少し早く生まれて小さかったが、目がクルクルしてとても可愛い赤ん坊だった。長男、次男と名前は、主人の希望で甲府のお父さんが名付け親なのである。二人の子供の母親になった私は、育児に追われながら、やはり初めての経験で、子供の異常を知るのが遅く、健夫の様子がおかしいなと気が付いたときは既に疫痢(えきり)に掛かっており、ほとんど危険な状態になっていたのである。かかりつけの小児科の先生に来ていただき、すぐに手当をしていただいたが、今夜一晩が山だといわれ、先生は付ききりで徹夜してみてくださった。点滴注射が朝まで続いて健夫はよみがえった。今思い出しても胸が痛い。と、同時に我が子のように健夫の枕元で一夜を明かしてくださった先生のご真情が身にしみて有難く思えるのである。私の未熟な母親としての失敗であった。 そうこうするうちに昭和十七年九月十一日、三男道彦誕生となる。今度は親である自分たちで名前を考えようと言うことになって、あれこれ考えたが、結局私の好きな道という字をとって道彦と名付けた。道、は人の道、正義の道、あやまってはいけない大切な道である。我が家は赤ん坊の他にまだ幼い子供が二人も居て、とても私一人の手では支えきれず、母が田舎からねえやをよんでくれた。おむつを洗ったり赤ん坊を負ぶってくれたりとても助かった。新聞社に勤める主人のかえりはいつも遅いのが普通だった。 さてここで再び、思っても見なかった大事件がおこる。太平洋戦争の勃発である。昭和十六年十二月八日、日本のハワイ湾攻撃から始まって、日米が正式に宣戦布告をし、戦争が始まったのである。初めのうちは勝利勝利で勢いが良かった日本軍も、次第に負け戦となり、アメリカのB29が飛来するようになって、焼夷弾が落とされるようになると、沢山の犠牲者も出るようになった。もう、竹槍方式やバケツリレーなどの訓練ばかりしていた銃後の国民は、さすがに馬鹿馬鹿しい思いを持った。隊をくんでB29は日に何度も襲来した。家毎に防空壕を掘っていたが私たちは空襲警報がなると、あわてて壕の中へ入らねばならなかった。子供三人を抱えて防空壕にはいるのも大変なことだった。主人は新聞社で色々情報を聞いていたので、次第に都心へと迫ってくる敵の計画を察知でき、もう、今、家族を疎開させねばと思ったのであろう、私たちの疎開を考えはじめた。 昭和十九年二月、私たちは長崎県島原市(母の実家)に疎開した。しかしここは町中ではあるし、田舎といえども安全ではない。母が知人に頼んでみると、安中と言うところに親戚があってそこなら大丈夫だという。行ってみるとなるほど雲仙の麓で、農家ばかりの村である。こんな山の中には爆弾を落とすこともあるまいと思われた。お願いして一部屋貸していただくことにする。主人はそのとき朝日西部本社(小倉)に転勤していたし、たまには安中まで帰ってきてくれることと、まずは一安心した。幸い大家さん一家は皆親切で、よく面倒を見てくれた。若夫婦の方にはちょうど健夫と同じぐらいの男の子がいた。私たちが借りたのはこの家の一番大切なお座敷だったので、少々気になったが仕方がない。私と三人の子供(照子はまだ生まれていない)の疎開生活がこうして始まったのである。 大家さんのおじさんは早速私たちのために庭の片隅に小屋を建てて炊事が出来るようにしてくださったり、竈(かまど)も作ってくださった。お米もたまには分けて貰い、当時の雑穀混じりの少ない配給米が潤ってとても有難かった。それでもこの土地になじむことは大変なことだった。水は川の水をくみに行かねばならない。飲料水には、漉し布を使って水をくみ、土地の人は大きな水桶を天秤棒に担いで運ぶのである。私はとてもそんな力はないので、バケツで何回も運ばねばならない。大変だった。洗濯するにも、別の場所の川へ行く。道彦はやっとちょこちょこ歩ける頃で、私が洗濯に行くときは必ず付いてくる。そして大きな石の上にのって、私の洗濯が終わるまでおとなしく待っていた。健夫は、ここで学齢に達し、安中小学校へ通うことになる。田舎の子供達は元気者だけれど、やはり言葉が方言なので健夫とは話が通じない。僕の言葉がおかしいと言って笑われたと言うこともあった。 こんな山奥でも一応警報はなる。それは有明海を隔てて向こう岸は大牟田という軍需工業地帯になっているので、この安中の上を通ってB29は攻撃に行くからだ。警戒警報がなると学校では直ちに生徒を家庭に帰さねばならない。そんなとき、一番幼い健夫は足が遅いので、上級生のお兄ちゃんが健夫をおぶって走って帰ってきてくれることが度々あった。優しい村の子供達だった。 こうした日々が続いた八月十五日、私たちは信じられないニュースを聞いた。天皇陛下のお言葉で戦争は終わったと言われたのである。 重大ニュースの発表があると前もって聞いたので大家さん達と一緒に聞いたのだったが、まさか日本が負けて戦争が終わったなどと言われても信じることは出来なかった。これはデマだと誰かが言った。しかし嘘ではなかった。繰り返しの放送で本当なのだと分かったとき、私たちは声を上げて泣いた。 なんの為の戦争だったのだろう? 広島では前代未聞の恐ろしい原子爆弾で人々も街もろともに焼き尽くされ、ついで長崎にも落とされ、ここに至って敗戦を余儀なくされたと言うことか。 恐らく日本中の人々が、取り返しの付かぬ悔しさを味わったのではなかったか。 それでも戦争から解放され、もう電気をつけてもいい、爆弾も落ちないと思うと、その自由を得られた喜びは何物にも代え難く嬉しいものだった。今まで閉じこめられていた暗闇から、光り輝く外の世界へ飛び出したいような気持ちだった。長い間お世話になったこの大家さんのおうちともお別れして、私たちは山を下り、少し町中の一軒の家へ引っ越すことになる。音無川という大きな川の畔だった。川を挟んで向こう側に大きなお風呂屋さんのあるのが嬉しかった。しかし世情は益々厳しく、配給米は更にひどいものだった。ヒエ、粟、キビといった雑穀混じりの少量のお米が配給されるだけ。世の人々は争って農村へ買い出しに行く。でも私はとても出られない。その時私は四人目の子供を妊娠していたのである。 神の助けか、私たちのうちの隣に住んでおられた大家さんの娘さん(三十四,五才)の方が、闇米買いのブローカーをしていると聞いて、もうお願いするしかないと思った。彼女はいかにも丈夫そうで、力もありそうで、重い米の運搬も出来そうな感じの女性だった。早速お願いした。当時こういう闇米というのは取り締まりが厳しくて、せっかく遠くまで出掛けても途中で警察に没収されたり、なかなか成功する率は少なかったようである。それなのに彼女は人の通らない道を考えたり、色々苦労して買い出しを続けてくれた さてここで、私は4人目の子供を産むことになるのだが、このときも近所の方が大変力になって下さった。初めての女の子で喜びもひとしおだった。暗い世の中を明るく照らしてくれるようにと願って、照子と名付けた。照子が三ヶ月ぐらいになったとき、主人が思わぬ話を持ってきた。下関の小月と言うところに朝日の人が居て、その人がまもなく東京本社に転勤するという情報を得て、私どもが少し前から同居の形で入らないと今は難しいので、何とか入りたいと考えていると言うことだった。にわかに移転と言うことになった。いよいよ本土に帰れるのだという喜びがあった。関門連絡船に乗って、遠ざかり行く九州の明るい灯を眺めながら、私は感無量の涙を流した。 小月と言うところは下関市ではあるが、市のはずれの小さい町だった。それでも我が家のある中村住宅(市 さて、この方々もいよいよ東京へ向かわれ、この家は完全に私たちの家になった。今まで主人は一人小倉での生活で、滅多に疎開先には帰れなかったが、今度はいよいよ家族揃っての生活が出来るわけである。思えば長い不自由な生活を強いられていたものである。 健夫は小三,乙彦は小一だったと思う。小月小学校に転校して初めて
時は移り、主人は再び転勤で東京勤務となる。そして私たちも中村住宅から少し離れた杉迫官舎に移ることになる。 ここは戦時中海軍航空隊の将校さん達の宿舎であったらしい。前の住宅に比べればかなり広く、高台で、景色も良い。庭の西南から眺めると遙かに瀬戸内 さて時はいつしか過ぎて、健夫は中学から高校へ入学することになる。下関西高等学校というのは、このへんではもっとも程度の高い高校であったが、無事入学できて本人はもとより、私どもも一安心したのであった。しかし一方でこのままいつまでも小月に居座っていていいのだろうかという不安があった。四人の子供達の将来を考えるとやはり東京へ早く行った方がいいというのは明らかだ。東京の大学へ入らせたい、主人も私もそう願っていた。またまた引っ越しを考えることになる。でも今度は最後の引っ越しなのだ。 東京にいる主人から頻繁に情報が寄せられるようになった。日曜毎に物件を探しているようだった。しかしなかなか格好の物件は見あたらない。何ヶ月か経ったある日、例によって送ってきた手紙が、私の目を引いた。それは新聞紙上で見つけたというこの家、これこそが今、現在住んでいる田無の家だったのである。古い家のようだが敷地が百坪近くある。庭が広ければ将来建て替えることも出来る。間取りも何とか親子六人が住めそうだ。主人も私も気に入って早速この家を買う手続きをすることになった。ちなみにこの家の住人だった人は(公務員)で都内に土地を買って新築されたのでこの家を売却することになったとのこと。 昭和三十年一月、私たち家族は、様々な思い出を残して、この小月の町を去ることになる。それにしてもここへ辿り着くまでの何と長かったことか。主人との別居生活も八年近くかかっていた。東京に着く。電車を乗り継いで田無の駅に着く。東京といってもここは一時間ぐらい西へ来た武蔵野台地のただ中である。田無駅から歩いて二,三分。 ところがこの田無という町、意外と保守的で、古い習慣が残っているのだった。戦後十年余も立っているのに未だ戦時中の回覧板が続いている。婦人会も半強制的に入らされ、「日掛け」と称して毎朝二十数軒の住宅を当番が回って小金を集める。昔ながらの「頼母子講」とか言う相互扶助目的ではあっても昔風のやり方を今なお婦人達の間でやっているのには驚いた。しかし「郷にいれば郷に従え」という格言通り、入らねば仲間はずれにされる。最初から仲間はずれにされることはすべてに影響してくると思って、私は入会した。いかにもその「日掛け」なるものの正体は建前で、本音は戸毎に訪ねておしゃべりをする。そういう場合のおしゃべりはもっぱら近所のうわさ話に尽きるのである。朝の忙しい時間をつまらない話に無駄遣いすることに私は抵抗を感じながら時期を見て脱会しようと思っていた。後日、それは実現した。 それより中学、小学と学校の用事で出掛けることが多くなり、私はいつしかPTAの役員を仰せつかっていた。子供を沢山預かっていただいている私にとって、少しでもお役に立てばと、この時期、私も及ばずながら働かせていただいた。そのうち、さすがに部屋が狭く感じるようになり、主人が当時新しく住宅建築として開発されていた組み立て式のミゼットハウスを我が家の東側に一部屋、子供達の勉強部屋として作ろうではないかと提案し、これも直ちに実現した。四人の子供達は机を並べ、母屋と遮断したような感じの勉強部屋で、夜遅くまで机に向かっていた。 いつしか健夫は早稲田の学生となり、乙彦は立川高校へ、続いて道彦も戸山高校へと進学していった。私はもう子供達の世話を焼かなくても良かった。自分のことを考える時期が来たのだと思った。何か社会の為になることがしたい。そんなある日、電車の中で一人の男性が、立ったままで、点字の勉強をしている姿を見た。私は瞬間、「これだ」と思った。点訳! これは確か通信教育で出来るはずだ。何か心ときめいて家へ帰り、子供達に話したところ「やってごらんよ、お母さん」と励ましてくれた。高田馬場の点字図書館から道彦が資料を貰ってきてくれ、早速手続きも済ましてくれた。皆の声援を受けて私はこの日から点字板と向かい合うことになるのである。今でこそコンピュータで処理することも出来るが、当初はすべて人の手によるものだった。点字板があり、点筆があって、一字一字打って行かねばならない。先ず五十音の点字を覚え、いろいろの約束事を覚えて文章がすらすら打てるようにならねばならない。点字図書館から送られてくる問題の用紙を間違いなく打てなければ次へ進めない。ミスが在ればもう一度やり直してくださいと厳しく送り返される。何度送り返されたことか。でも皆に励まされながら頑張っているうち一年余、遂に願望の資格を取ることが出来たのだった。 それからの私の日常は変わった。点字板はいつも私の机の上に乗っている。暇さえあればコツコツコツと打っている。対象となる本は、係りの先生が選んでくださるのだが、私はもし許されるなら自分の読みたい本を打てれば幸せだなと思って伺ってみると「いいですよ」と快く許して下さった。読みたかった本が読めて、同時に点訳も出来る、これは二重の喜びだった。昭和四十一年、第一巻(井上靖著、「魔の季節」)を納巻したときの感激は忘れられない。こうして平成元年四月まで二十三年間、私の点訳は続いた。この間に全国各地の読者(盲人)の方々から沢山お礼状を頂いた。点字で送って下さるお礼状は私の大事な宝物だった。北海道や沖縄からも頂いた。そして百巻を過ぎた頃、図書館から思わぬ知らせを頂いた。毎年1回催される「日本盲人社会福祉協議会」から私に感謝状が渡されるとのこと、なんだか夢のようであった。思えば多少なりとも社会のためになればと始めた奉仕であったが、実際は私自身の生き甲斐を与えていただいたというのが真実だった 何か、肩の荷が下りたようでもあり、一抹の寂寥感もあって、私はかねて聞いていた池袋の西武デパート八階のいわゆるコミュニティーカレッジを訪ねてみた。驚いたことに文学、美術、音楽、体育すべての教科が揃っていてお好み次第といった感じ。書道の中に写経教室が見あたった。私は昔から兄姉弟を早く失っているし(この自分史の中には遂に書けなかったが、兄の他に一番上の姉、そして八つ下の弟、と次々に早く死に別れている。)そんな悲しい経験を持っているだけに、何とかして亡き人々の霊を慰めたいといつも思っていた。写経を習いたいとは前から思っていたので、その場で申し込んだ。目的は「般若心経」である。昔、母たちが毎晩お線香を上げて、この「般若心経」を唱えていた。私も知らぬ間に暗誦出来るようになっていた。短いお経だけれどすべての知恵が凝縮されているお経だと聞いていた。お手本を頂いて、墨をすり、静かに筆をおろす気持ちは、既に雑念を離れ、仏道に帰依したような気持ちになるから不思議である。週に一度のこのお教室は待ち遠しいものだった。ここで出会った友がもう一つ写仏を習っていると聞いて、誘われるまま出掛けたのは、芝の道成寺だった。彼女の実家の菩提寺で前から来ているという。大広間で沢山の人が机の前に正座していた。お住職様のお話があった後、仏画のお手本が配られ、之は文字通り半紙に写していく。最初は地蔵尊の仏画であったと記憶している。写経、写
さてここで一転換、もともと焼き物に興味のあった私は、つづいて「陶芸教室」に通うことになる。自分でお茶碗やお皿など焼いてみたいというのが夢だった。新進作家、芸大出の先生が指導してくださり、お教室は活気にあふれていた。大体が中年の女性で四,五人男性が混じっていた。私のような老年の方も二,三人おられたようだ。 初めて手にする土の手触り、なんというか子供の土遊びを思い出す懐かしいものだった。手ろくろに乗せ、好きなように形作っていく。最初の作品は湯飲み茶碗だったと思う。素焼きをして上薬をかけ、本焼きをすればできあがり。 次第に難しいものに取り組み、これはなかなか奥が深いと思った。それだけに興味は尽きないのだが、一番大変だと思ったのは土練りだった。力を入れて土の中の空気を押し出すように練る。その練り方がむずかしい。俗に「土練り3年」と言うそうだが私は最後まで満足に出来なかった。でも先生に助けていただいて、作品は面白いよう 振り返って考えると私は長い人生、運命の波のまにまに、ある時は沈没寸前の時もあったし、穏やかな波と共に、平和なときもあったし、様々な体験をしてきた。しかし総合して幸せな部類に入れるのではなかろうかと自分で思っている。長い老後は夫婦がお互いに相手を思い、個性の違いを認めてそれぞれの生き方を容認することが大切だと私は思ってはいるし、実行してきたように思う。 寿命は神のみが知る。 それまでは一族が健康で親交を重ね、益々繁栄して貰いたいと願うばかりである。 <二〇〇三年(平成十五年)八月二十六日> |